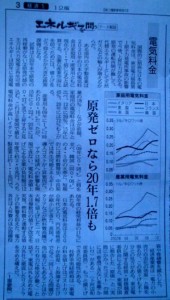エンディング・ノートは考えれば考えるほどわからなくなる映画だ。死にたいと思っている人も世の中には沢山いるから、そういう人にとってはためになると思うが、生きたいと思っている人はそれ以上沢山いると思うので、そういう方々には良くない映画だと思う。
世の中には「願望成就法」なるものが多く存在しているが、そのなかでも定番なのが、ノートに自分の夢をできるだけ具体的に書いてみるという方法だろう。例えばお金持ちになりたいという方は、具体的に金額を書く。10億円とか、100万円とか。車が欲しいという方は車の名前を書いてみる。ベンツ500SL(こんな車あるかなぁ?、興味がないので確証ありません)とか。
エンディング・ノートは、この「願望成就法」をなぞったもの。ということは、つまり、お父さんは、死にたかったといえるのではないでしょうか。この映画でわかることは、具体的にノートに書き連ねた言葉は力をもち、家族や医者、および関連スタッフに共通の認識と力を与え、死の具現化のためまっすぐにゴールへと突進してしまったということです。ドキュメンタリーながら、この映画のエンディングシーンは、作り込まれたものとなり、つまらないものになってしまいました。
誕生や死は、たとえば、ゲーテが、最後に「光をもっと光を」といったり、道長が、「極楽浄土」を願ってひもを手にとったり、人生の中でも、作為的な嘘のようなものが入る隙のない、当事者の真実がほとばしる数少ないシーンの一つであると思うのですが、お父さんは最後の最後を当たり前といえば当たり前の普通名詞の「死に際」にしてしまいました。それがいいんだ、といわれれば、何ともいいようがありませんが、それでも、結局、このお父さんは何者だったの?という疑問が私の中では残り続けております。
大会社の取締役とのことだが、業績は残したのかな、一つ二つは紹介してもらいたかった。就職以前、進学などには自分の意志は介在したのだろうか、先生とか進路指導のまま考えることなく進学、就職したのだろうか。奥さんとは恋愛なのだろうか、挫折体験はなかったのだろうか。夫婦関係、親子関係はどうだったのだろうか。かなえた夢は、最後の死以外にあったのだろうか。疑問はキリがないが、・・・なにも見えない。
ソニーとの取引に失敗したとのことだが、それはそのままだったのだろうか。反省はあったのだろうか、あったとしたらそれはどのように生かされたのだろうか。仏教の葬儀はお金がかかるということでキリスト教にしたのだが、いくら節約になったのだろうか。仏教とキリスト教以外の選択は何があったのだろうか、なかったのだろうか。節約ということなら、究極として墓などいらないということにはならなかったのだろうか。川とか海に灰を投げるというのはどうだろうか。
キューブラー・ロスは「最終的に自分が死に行くことを受け入れる段階」として死の受容のプロセス(否認→怒り→取引→抑うつ→受容)を表しているが、そのようなものはこの映画では見られなかった。このプロセスは、否認とか怒りの間に、医師や医療への疑問とか怒りを経ることになり、たとえば、病院や医者を変えてみたり、丸山ワクチン(今もあるのかな?)ゃ他の療法を試したりということになるのだが、お父さんはそのような事はなかったのだろうか?治るとか治療するという、つまり生きる意志がそもそもあったのだろうか。なにも見えないのだ。最後までなにも見えないのだ。映画はひたすら、凡庸な死にむかっていくだけだ。
普通は、そうだなあ、家族の中にも「鬼っ子」みたいな、出来損ないで頭や素行が悪いのがいて、それが、映画を撮っているのに怒ってスタッフを蹴り散らかしたり、医者に悪態を付いたり、無理矢理退院させたり、理屈じゃできないことを平気でやらかして、その場や空気に冷や水を浴びせたりして、結果的にお父さんを救ったり、そこまで行かなくても、遺産相続なんかでもめて、葬儀をめちゃくちゃにしたりして、生気あるお父さんの一生を創り上げたりしないかなと思うんだけどなぁ、どうなんだろう。
懸念するのは、ベビーブームでうまれて、ベルトコンベアに載りっぱなしで生きてきて、気が付いたら死が近づいてきた。とはいえ、ベルトコンベア以外の選択は経験がないため、そのままベルトコンベアにしがみついてしまったら死んじゃったということだった・・・、そういうことだったのではなかろうか?そんなことがあるのだろうか?・・・、十分にありそうだな。家族のあり方を含めて、考えさせられる映画ではありました・・・。
最後に、E・キューブラー・ロスの貴重な講演集「死後の真実」巻末にある、阿部秀雄の解説き部分(キューブラー・ロスの略歴みたいになっている)を以下に紹介したい。キューブラー・ロスの「死」に対する真摯さに鑑みてこの映画を精査すれば、わたしがこの映画にもつ疑問が少しでも理解していただけるのではないかと思う。
死のセミナーの時期
エリザベス・キュープラー・ロスは一九二六年、スイス、チューリヒで生れた。義務教育を終えると、父親の反対を押し切って医師への道をめざした。住み込みの家政婦などをして働きながら大学入学の資格を取り、一九五七年チユーリッヒ医科大学を卒業する。結婚してアメリカに渡り、一九六五年にシカゴ大学に研究員として入局してから、りん死患者のベッドサイドを訪れて、死にゆく人の話し相手になり、悲しみの克服と死の受容を助けるという、これまで誰も手を付けようとしなかった仕事を始めた。
数多くの患者と体験を共にするうちにロスは、重症のがんだという衝撃的な宣告を受けた患者が経ていく心の動きに共通するものがあることに気づく。まずはその事実をかたくなに否認することから始まって、怒りを激発させ、取り引きを試み、あきらめて悲嘆に沈む時期を経て、安らかに死を受容してこの世に別れを告げるまでの五段階である。後になってこれは、たんに、りん死の体験にかぎったことではなく、その人にとってかけがえのない大切なものを喪失するときつねに体験する現象だということが明らかになった。
シカゴ大学に入局してまもなく「死のセミナー」を開始し、一九六九年には『死ぬ瞬間』を出版した。この最初の著書がベストセラーになり、また国際的なライフ誌で大きく取り上げられるなどしてその業績が広く世に知られるにつれて、ロスはアメリカ国内はおろか、世界各地を超多忙のスケジュールで飛び回るようになる。なお、ここで紹介しているロスの半生については、デレク.ギル著『「死ぬ瞬間」の誕生』〔貴島操子訳、読売新聞社)を参照した。
医者が生かすことでなく死ぬことに目を向けるなどというのは、当時としては異端視さえされかねない画期的な仕事だったが、今日では終末期医療やホスピスの先駆者として高く評価されている。この時期のロスの仕事を特徴づけるキーワードは、来るべき<死>ないしは<喪失>の〈受容〉をどう援助するかであった。
癒しのワークショップの時期
少数の人たちを相手にもっと深い交流ができるのではないかと思うようになったロスは大学を辞め、病床で個々の患者と輝くような最期のひとときを共にするほか、集団による癒しのワークショップに力を入れるようになる。最初のワークショップが試みられたのは一九七〇年。これが成功に終わったので各地で開かれるようになったが、やがて一九七七年になるとシャンティ・ニラヤと呼ばれる本拠地が建設される。
時とともに、ロスが主宰するワークショップは、りん死患者のための死への癒しにとどまらず、広くさまざまな苦悩をかかえた人々を含めた、生と死の癒しの場へと発展していく。五日間のワークショップに参加した人たちは、いつしか心のよろいをはずして感情を解き放ち、心ゆくばかり怒りをぶつけ号泣したあとで互いに抱き合い、許し合い、じぶんと他人を愛する力を取り戻して、まるで別人に生まれ変わったかのように、見失っていた自じぶんを取り戻す。
この時期の特徴は、来るべき死に気持ちを向ける前にまずベクトルを逆にして、生まれてからこの方、根深いところに閉じこめてきた苦痛の感情を、無条件の愛に包まれた安心感に支えられて解き放つのを助ける仕事が本格化してきたことである。キーワードは過ぎ去った<生>の<癒し>であり、そのことで残されたこれからの生がますます輝きを増すことになる。
それとともに、りん死患者の体験やじぶんじ身の神秘的な体験に促されるようにして、合理的な医学教育を受けてきたはずのロスはしだいに、死後のいのちへの確信を深めていく。過去の癒しとともに未来からの希望が、いわば両面からりん死患者を支えるようになる。でも、それについては、この時期にはまだまだあまり声高に言われることは少なく、副次的な位置を堅持していた。
ロスにはこれまでに多くの著書があり、最初の著書『死ぬ瞬間』〔原著一九六九年)をはじめとして、『死ぬ瞬間の対話』(一九七四年)、『続・死ぬ瞬間』(一九七五年)、『死ぬ瞬間の子供たち』(一九八一年)、『新・死ぬ瞬間』(一九八三年)、『エイズ死ぬ瞬間』(一九八七年)の六冊が、デレク・ギルによる伝記『「死ぬ瞬間」の誕生』(一九八○年)とあわせて「死ぬ瞬間」シリーズの形で読売新聞社から刊行されている。また、E・キューブラー・ロス文/M・ワルショウ写真『生命ある限り-生と死のドキュメント』(一九七八年)と『生命尽くして-生と死のワークショップ』(一九八二年)が産業図書から刊行された。
こうした一連の著書をいま読み返してみると、死後のいのちに関するロスの確信が、実はかなり早い時期から少しずつ、控えめな形で表明されてきていることに気づく。すでに二冊目の、一九七四年の著書『死ぬ瞬間の対話』のなかで、質間に答える形で、「死後のいのちを一点の疑いもなく信じている」「肉体は死ぬが精神ないし霊魂は不死だと信じている」と、言栞少なにだがきっぱり言い切っている。翌七五年に出された『続・死ぬ瞬間』では、「ケムシがチョウになるように」という比喩が現れる。しかし何かと考えるところがあったにちがいない。こうしたことを正面から著書に書くことにはかなり慎重だったようである。
『ダギーへの手紙』と『天使のおともだち』
その例外の一つが文中にも出てくる『ダギーへの手紙』〔アグネス・チャン訳、はらだたけひで絵、佼成出版社)である。これは、一九七八年に九歳の脳腫瘍にかかった男の子ダグ・トゥルノからもらった手紙で投げかけられた、「いのちとは何なの?死ぬってどういうこと?子供が死ななくてはならないの
はなぜ?」という切実な質間に心を打たれたロスが、この本で曹かれているのと同じような内容をはっきりと、子供にも分かるようにやさしくかみくだいて、フェルトペンを使った色彩豊かなイラストを添えて出した返事である。ダギーの宝物になった手紙は、手から手へと渡されて多くの親子に読まれていたが、とうとう手書きの字や絵をそのままに出版された。
この十ページほどの、まるで絵本のような小冊子のなかで、ロスは何よりも神様の愛を強調している。ちょうど太陽のように、神様の愛はいつでも、たとえ雲にさえぎられて私たちの目に見えないときでさえ、私たち一人ひとりをあたたかく照らしてくれていること、その愛は無条件の愛であること、子供は神様に送られて自分の親を選んで生まれてきたこと、親の成長や学習を助けることができること。
生きるとはちょうど学校のようなもので、私たちは生きているあいだに、愛すること愛されることを含めていろいろなことを学ばなくてはならないこと、
神様がら出された試験に合格すると、そこを卒業して私たちがやってきた古巣に帰ることができること、そこはもう痛みなどなく、親しい人たちと再会し、楽しく歌ったり踊ったりできること。
「死ぬことはマユから抜け出て美しいチョウになるようなものだ」という比喩がここで絵入りで使われている。「春に捲かれ、夏に咲き、秋に実り、冬に枯れる」とか、「水平線のかなたに行ってしまった船は目に見えなくなるだけで、消えることなどないのだ」とか、「夜になってもまた朝がくる」とか、いろいろなたとえを使って、死後も続くいのちについて伝えようとしている。
もう一つの例外が、一九八二年に書かれた『天使のおともだち』(伊藤ちぐさ訳、金子千晶絵、日本教文社)というすてきなファンタジーである。男の子ピーターが重い病気にかかって死に、ピーターを愛していたおとなたちも、大なかよしだった女の子のスージーも悲しみの涙を流すが、スージーの悲しみはおとなたちとはちょっと違っていた。それというのも、ふたりはいつも天使と一緒に遊んでいろいろなことを話していたし、ピーターが亡くなる少し前に天使に導かれて肉体を離れ、愛としあわせに満ちた美しいあちらの世界に旅したことがあるからだった。
本来の仕事と取り組む時期
ところが、ワークショップの仕事が軌道に乗ってきた頃ロスは、本文に書かれているように、死にゆく患者を椙手の役目はもう終わった、という啓示を受ける。すでにロスの代わりとなる人はたくさんいるし、ロスがこの世にいる当の理由は、死は存在しないという〈死後の真実〉を人々に伝えることであって、これまで取り組んできたことは、この仕事をやりぬくための苦難や酷使や抵抗に耐えることができるかの試験台だった、というのである。
こんなふうに死にかかわるロスの仕事の歩みを三つの時期に分けてみたが、もちろんこれは便宜的なもので、新しい時期の仕事を特徴づける要素は古い期に芽生えているし、新しい時期を迎えたからといって古い時期の仕事の意味が薄れるというものでもない。
それにしても、あらゆる時期を一貫して特徴づけるキーワードは何かと間われれば、それは無条件の〈愛〉のエネルギーだと答えたい。
現代のシャーマン
重症の患者から臨死体験についていろいろ見聞きするのと前後して、ロス自身も霊的な存在との触れ合いや超越的な体験をすることが、死ぬ瞬間を共にする仕事を始めるずっと前からいろいろあったらしい。
愛と霊感のカを借りて、この世の生と死後の世界とを仲立ちする人ー。これはまさにシャーマンだが、ロス自身も、自分はシャーマンだと称してはばからない。これには、行ったこともないインディアン部落の夢見や、実際に部落を訪れたときの懐かしい既視感や、催眠退行による体験がからんでいて、ロスは自分がかつて前世でインディアンだったと信じているようなのである。
当時朝日新聞社の編集委員だった飯塚真之さんが取材した「こころ」の頁(朝日新聞、一九九〇年十二月三日朝刊)によると、ロスは、親交のある精神科医の卜部文麿(うらべふみまろ)さんに向かって、「あなたもシャーマン、私もシャーマン、インディアンのシャーマンは癒しを意味するが、私たちも現代の医師として立派なシャーマンです」と語り、「私は2003年まで生きます〔七十七歳になる)。あなたもそれまで生きてください。でもその年に死ぬことが決まっています。なぜって、昔からそう思っていた」とも語ったという。
死後の真実がはたしてロスの言っているとおりかどうかについては異論もあるかもしれない。しかし、ロスの偉大なところは、たんにりん死体験について世界で最初に関心を持ち本格的な研究をしたのがロスだった、というだけではない。興味とか研究とかの前に、何よりも死に臨む人たちとの深い愛と学びに動機づけられているところが私たちを感動させるのではないだろうか。
人類全体が長いこと物質本位に走り続けたあげく大きな危機にさしかかっいる今日、この本は、私たちに見えない世界を見るように促し、新たな目覚を誘う重要な意味を持っているように思う。
【付記】本書が刊行されてから、キューブラー・ロスの著書が二冊邦訳された。一冊は『「死ぬ瞬間」とりん死体験』(鈴木晶訳.読売新聞社)で、本書と同じようなテーマについて取り上げた七つの講演を集めたもの。多少重複する内容もあるが、これはこれで一読に値する。もう一冊は『人生は廻る輪のように』(上野圭一訳、角川書店)で.これはロス博士自身の手によって書かれた自伝である。デレク・ギルによる伝記『「死ぬ瞬間」の誕生』の記述が一九六九年末、つまり「死のセミナーの時期」で終わっているのに対して、それ以後の「癒しのワークショップの時期」、さらには、死後の真実を人々に伝えるという「本来の仕事と取り組む時期」についても多くのページが割かれている。仕事から引退した七十一歳のロスはこれが事実上の絶筆になるだろうと述べている。
【付記2】二〇〇四年八月二十四日、ロスは自分が予感していた時期より一年だけ遅れて、マユから抜け出して美しいチョウになった。