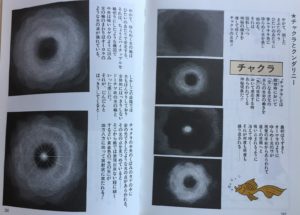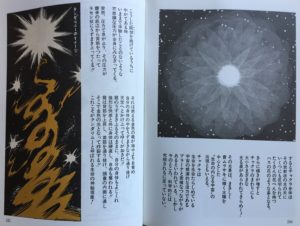「往生要集」の著者、源信のターミナル・ケアは進んでいたらしい
60歳を過ぎたということも有り、最近は死に方について考えることが多くなったような気がする。昔は気にもしていなかった浄土宗や浄土真宗の西方浄土の話なんかに惹かれるようにもなってきた。何か月か前に読んだ本で、浄土教の基礎を築いた源信なんかは、かなり進んだターミナルケアをしていて、近親者のターミナルケアは、死に行くものが現世に執着をもつようになるので、近親者以外の看護が望ましいような教えしていたらしい。
そのあたりを読み直してみようと、今日は時間をかけて本棚を弄っていたのだが、目的の書物が見つからなかった。確か、寝たきり老人や、植物人間とのコミュニケーションについて語っていた本だと思ったのだが、題名も忘れているのだからしようがない。いずれ、時期が来たら現れるのだろうと思うことにした。
代わりと言ってはなんだが、生、死、神秘体験―立花隆対話篇に浄土教についての似たような記述があるのに気づいた。なかなか面白かったので、ご紹介。
臨死体験が語るもの
立花 今度、「文藝春秋」に三年近く連載した「臨死体験」という作品が完結するんですが、これはおそらく、僕がこれまで書いてきたものの中で、いちばん読者の関心が高かったように思うんです。僕自身、そのあまりの反響の大きさに、ややとまどっているといった状況なんですね。
臨死体験へのそういった関心の深さというのは、人がやはり死というものをいろいろな意味でかなり強く意識している.そういう時代背景があるんじゃないでしょうか。一つには世紀末ということもあるだろうし、高度医療化時代を迎えて、脳死間題、尊厳死問題、ガンの告知問題などを通じて、みんないやおうなしに死の問題を考えざるをえなくなったということもあるだろう。あるいは環境聞題で、地球の死というような終末論的状況を考え蔽ければならなくなったということもある。
先生には取材の段階で平安末期の浄土信仰や「二十五三昧会(にじゅうござんまいえ)」という念仏結社について教えていただきましたが、あの時代がやはり、末法思想という一種の終末論が流行った時代ですね。
山折 そうです。
立花 ちょうど社会体制も平安から鎌倉へと移行する大転換期で、社会経済的にも、いろんな混乱があり、やはり人が死というものを強烈に意識せざるをえない状況があった。その中で、死んだらどうなるのか、死んだあと、極楽浄土へ行くにはどうすればいいのかという関心が非常に高まったわけですね。
山折 そうです。日本では死後の世界の概念がつくられていくうえでは、やはり浄土教の影響が大きかった。この浄土教というのは、もちろん元はインド仏教の一派なんですが、とくに人間の死後の運命、人は死んでのち、どこに「往生」するかということについて考察をめぐらせた一派です。その浄土教が日本の民衆のあいだに浸透していった時期が、だいたい平安の中期から末期.『源氏物語』が書かれた時期になります。そのころ、比叡山に源信(九四二~一〇一七年)という僧が出て、『往生要集』という本を書き、日本の浄土教の基礎を築いた。これはいわば死のためのテキストで、地獄や極楽のイメージ、極楽往生のために行なうべき信仰生活について詳しく説いたものです。一般の人々にも広く読まれ、その後の日本人の地獄観、極楽観の形成に決定的な影響を与えています。
この本を書いたあと、源信は実際に念仏結社をつくって、極楽往生のための実験を行なうわけです。同志たちと毎月一五日の満月の日に集まって、徹夜で念仏を唱えた。この結社には、二五人の人間が集まったので「二十五三昧会」という名がつきました。
彼らはメンバーの中の誰かが病気になって死を迎える段階になると、その病人を「往生院」という特別の部屋に入れてやる。そして仲間のうち二人がつきっきりになって、二四時間体制でいっさいの世話をした。いまでいうホスピスのようなことをやったわけです。立花 それで、死んでいく人が本当に浄土へ行けるのかどうかを確かめるために、病人の耳に口をつけて「いま何が見える?」と聞いたりしたわけですね。そしてその人物が見た最後のビジョンを記録した。
山折 そうです。その記録はかなり残されていて、それを読むと「真っ暗闇だ」と答えている人がいるわけです。「地獄の業火みたいなもの述身に迫ってきて苦しい」と言っている人もいる。しかし、中にはやはり「極楽が見えている」とか、「阿弥陀如来が自分に近づいてきている」とか、今日言うところの臨死体験的なイメージを見ている人がいるんですね。
立花 そういう記録からみると、やはり臨終の床で、ほとんどの人はそういうビジョンを見るということが言えるんでしょうか。
山折 というより、彼らのは念仏結社ですから日常的な修行をやっているわけです。その修行の最終的な目標は、死ぬときにいいイメージを見て死にたいということだった。そのための修行であり、その修行に成功した人はいいビジョンを見ることができるということだったわけです。
それは二十五三味会だけでなく、同時代のほかの修行者たちも同じです。死ぬときに良きビジョン、つまり極楽のイメージを見て死ぬためには、それ相応の身体訓練をしなければならないという自覚があった。それで、お経を読んだり、山を歩いたり、写経をしたり、禅を組んだり、いろいろなことをやる.そして、いよいよ自分の寿命が尽きた、あと一カ月かニカ月で息を引き取るかもしれないということを悟ると、穀断ちをする。五穀を断って木の根・木の実のみを食べる木食を行なって、白分の体を枯れ木のような状態にしていく。そして、もうあと一日かそれぐらいで命が尽きるというときに、完全断食の状態に入っていくわけです。
そうすると、人間の生理というのは非常におもしろいもので、無限に死の状態に近づいたところで、ある種の生命力の反発のようなものが起こるのか、ビジョンを見る。そのビジョンの多くが「阿弥陀如来が現われてきた」とか、あるいは「極楽が現われてきた」というものです。そして翌日息を引き取る。つまり生命の限界ギリギリのところでそういう現象が起きることを彼らは経験的に知っていたということですね。立花 その時代の人たちは、そのイメージというか、ビジョンというものを、どう考えていたわけですか。そこで見ているものは単なる視覚体験ではなくて、本当に浄土世界そのものである、つまり人が死んだあとの世界そのものを自分は見ているんだという意識があったわけですか。
山折 この世からあの世へしだいに近づいていって、そして浄土のビジョンを見たのだという確信を持っていたでしょうね。
立花 断食鞍どを経て、自分を枯らして死んでいくというやり方は、空海の入定もほとんど同じですよね。それから、時代が違うけれども、東北の出羽三山で断食してミイラになっていった僧侶たちも方法的には同じですね。
山折 そうです。
立花 そういったケースは知られている以外にも前からあって、その過程でそういうビジョンを見た経験の伝統が極楽浄土のイメージをつくっていったということがあるんでしょうか。
山折 いまおっしゃった出羽三山の即身仏のように、土に穴を掘ってそこに入って断食をする土中入定というやり方のほかに、薪を積んだ上に自分が乗って、自分で火を付けて焼くという、火葬の模倣のようなやり方もありました。それから、水中に身を投げて死ぬという水中入定みたいなものなど、いわば異常な状況をつくってその中で往生=死を迎えるというやり方は昔からずいぶんあったと思います。中国にもそういう例はたくさんあります。
立花 修行者たちがそこまで過激なことをするというのは、それが本当に極楽往生につながるという確信がないと、とてもできることではないですよね。そういう確信はどこからきているのか。たとえば土の中に入ってミイラになったお坊さんが、中で自分がどういう状態にあるかを外の人に伝えたというような記録はあるんですか。
山折 それは本人というより、最期を見届けた人々の記録が主です。死んでいく人が直接生き残った人に伝えた例というのは、さきほどの「二十五三昧会」ぐらいだと思います。秘伝の形で口から口へ伝えられた話はたくさんあるだろうとは思いますけれども。
立花 日本の古い文献を読んでみますと、臨死体験の記録というのは昔からずいぶんたくさんあるんですね。
山折あります。
立花 日本だけじゃなくて、外国の文献にも、たとえばプラトンの国家篇なんかにもちゃんとある。ああいうものを読んでいくと、臨死体験というのは、世界のいろいろな宗教の原体験として昔から、非常に大きな意味を持っていたのではないかという気がします。死にかけて生き返った人というのはいつの時代にも必ずいるわけで、彼らは白分の体験を現実のものとして人に語る。それがあの世のイメージをつくり、また、それを含んだコスモロジーというか、世界解釈をつくり、それが宗教を成立させていった。つまり宗教の原体験の一つとして、臨死体験は人類文化において非常に重要な意味を持っていたんじゃないかという気がします。
以前、取材でもうかがったんですが、先生ご白身が、やはり死にかけたときに臨死体験に近いものを経験なさってますよね。そのときの体験と、それが精神に与えたインパクトというか、世界観の変化というものを教えていただけますか。山折 私自身の体験は、はたしてそれが臨死体験であるかという間題もあるんですが、それはひとまずおくとして、私は学生時代に十二指腸潰瘍をやって胃袋を三分の二、切っているんです。それから一〇年ぐらいたって、学生諸君と酒を飲んでいたときに、突然、大吐血をして、意識を失いました。バケツ半分ぐらいの血を吐いたと思います。
その意識を失う瞬間に、眼前に五色のテープをふき流したようなイメージが現われたんです。相当血を吐きましたし下血もしましたから、生命力がかなり衰えている状態でのことで
す。五色のテープをふき流したようなイメージの中で、白分の体全体がフワッと浮遊した感じがした。それが非常に快かったというか、気持ちがよかった。何か大きなものに吸い取られていく、そういう感じがあったんですね。
これはあとから思い出したことなんですけれども、「まあ、このまま死んでいくならそれでもいいか。これはなかなか悪くないな」ということを、非常に短い時間だったと思いますが感じておりますね。立花 そのフワッとした感じの中で。
山折 そうです。何かに吸い込まれていくような心地よい感じの中でです。私の場合は臨死体験といっても、それがすべてでして、気がついたら病院で横たわっていました。その後三カ月間、入院したんですが、点滴をしながら一〇日間ぐらい絶食をしました。すると三日目、四日目あたりまではものすごい飢餓感に悩まされたのに、不思議なことに、五日目、六日目になると、気持ちが非常に澄んでくる。五感鑓非常に鋭敏になってくるし、体全体が軽やかに感じるんです。
立花 それは一種の断食体験に近いことなんでしょうね。
山折 そうです。それでベッドの上で、なぜこんなに自分の生理が変化したのかと思っていたところ、フッと思い浮かんだのが、さきほど言いました「二十五三昧会」という、平安末期の念仏結社の人々の体験だったわけです。彼らはなぜ修行の最後の段階で断食なんていうことをやったのか。それはやはり最後の最後に死を乗り越えるためのイメージが欲しかったからではないか。
それを自らの体験と重ね合わせたときに、人間というのはひょっとすると、生命が非常に衰えたとき、危機的な状況に追い込まれたときに、ある生命の反逆作用が起こって、超日常的なイメージを眼前にする。そういう現象が起こるのではないか。そう思いまして.私の人間に対する考え方とか、大きなごとを言えば、世界観がガラッと変わったわけです。自分自身の肉体がまさに研究対象になるといったらいいんでしょうか、そういうことを実感しました。立花 そのときまでは「死んだらどうなる」と思っていたんですか。いっさい無だと思っていたんですか。
山折 それまでは無神論者ですよ。観念的な無神諭者というのかな。死は無に帰することであるという近代ヨーロッパの考え方を受け入れていたと思いまずね。ただ、いまから思うと、それはやはり首から上の知識だったような気がしますけれど。
立花 それがその体験を機に、考えが変わるわけですか。
山折 ええ。それまで私は、死後のことを積極的に否定していたわけです。実在するかしないかということで言えば、とても実在するとは思えなかった。しかしその体験があってからは、確かに証明はできないかもしれないけれども、たとえフィクションとしても死後の世界というものを考えたほうが、人閻の生き方というのは豊かになるのではないか。そういうふうに感じるようになりました。 (32ページ~39ページ)
死んだら、どうなるか? 死んだらおしまいではなかった?
養老孟司氏が、人間は三人称の死は体験できても一人称の死は体験できないというようなことを言っているのを読んだことがあります。傍から見れば悲惨な死も、実際に死んでいく人にとってはそれほど悲惨じゃないのではないかというのは、充分に考えられることです。
わからない「死」が過大に美化されたり、忌み嫌われたりしがちではありますが、逆に軽く考えてみることも必要じゃないかとつらつら思っておりました。このたび、わかりやすい本に出会えましたので、ご紹介します。
| 死んだらおしまい、ではなかった 2000人を葬送したお坊さんの不思議でためになる話 |
著者は、昭和五十五年(1980年)から平成三年(1991年)にいたる11年余の間に、2000以上の葬儀を行った僧侶。ある喪主の方に、「成仏するんでしょうか?」と尋ねられ、答えにつまったことが発端で、葬儀の際に故人の状態に注意を払い続けるようになりました。そしていつしか、霊の実在を感じ取れるようになったというのです。体験と著者の実感から書かれたこの本は、説得力がありました。しかも、分かり易い。
ということで、以下に紹介するのは、人が死んだらどうなるかについてです。(p48~p57)
・・・亡くなった「本人」はどこにいるのでしょうか。
だいたいの場合、「本人」は遺体の近くにおります。
そして、遺族や僧侶が葬儀を行う様子をじっと静かに見ているのです。
葬儀の光景も遺族の方々の様子も、「本人」には見えています。声も聞こえているのです。けれども実はこのとき、2,3割くらいの人が、自分が死んだことがわかっていません。
ボケーっとしているというか、もうろうとしていて、呆然としている方が結構おられます。
だいたいの場合、私が通夜で感じる「本人」の様子は”キョトン”というか”ボケー”というか、要するに「なにがなんだかわからない」といった感じが多いのです。そして、お経をあげているうちに、もう少し進むと、「疑っている」という感じになるのです。「本人」が「自分は葬式の夢を見ているのだ」と思っていたり、またはそう思いこもうとしているようなのです。
「本人」には葬儀をしている光景はわかるので、ーどうも、自分の葬式をしているらしい……。
-ああ、自分は死んだのかもしれない。
-どうも死んだようだ。そうか、死んだのだ。と次第に悟っていくわけです。
そして、身体があればこそできた諸々のこと、ああしたいこうしたいという物事が、もうできないのだと気づいていくのです。いわゆる俗世の未練が絶ちきれていくわけです。そして、成仏へと進んでいくわけです。
このように故人に自分の死を悟らせ、俗世の未練を絶ちきらせていくのが通夜であり、葬儀の本質的な意義なのです。
なかには、身体と「本人」が分かれたときに、「本人」が十分に自分の死を悟っている、事態をのみこんでいる人もあります。そういう場合には、僧侶が来てわざわざ葬儀を執り行う必要はないとも言えるでしょう。しかし、実際には、まわりはわかっていても「本入」は自分の死に気づいていない場合が多いのです。
ー助かる、助かる。大丈夫、大丈夫。
と、思いながら亡くなっていく人が多いのです。亡くなると、病気で苦しんでいた場合など、その肉体的な苦しみから解放されます。ろうそくの炎が消えるときに急に大きくなるように、身体がよくなったような気がするようなのです。そのため、白分が死んだことには気がつかないで、
-自分の病気が治ったのだ。
と錯覚してしまう場合もあります。
だから、そういう人には葬儀という一連の儀式をして、自分の死という現実を気づかせてあげなければいけないのです。繰り返して言います。
葬儀とは、死によって身体と「本人」が分れたときに、その「本人」に対して遺された者たちや僧侶が、儀式な言葉でもって「あなたは、亡くなったのですよ」と教えてあげることなのです。そして、この世への執着や未練を断ちきってもらうのです。
これが枕経であり、通夜であり、葬儀を行う意義であるわけです。
よく「引導を渡す」という言葉をお聞きになるかと思います。
「引導」というのは、もともとは「手引きする」「案内する」というような意味ですが、人々を導いて仏道に入らせる意味で使われていました。
「引導を渡す」というと、とくに、死者を迷界から浄土へと導く儀式のことになります。「迷界から浄土へ導く」には、死者に、「自分が死んだという事実」を確実に認識させ、現世への執着を棄てさせて、悟りの仏道へと進むようにさせねばなりません。そのためには、「あなたはまちがいなく死んだのですよ」という事実を、
死者に宣言する儀式が必要になるのです。もはやこの世にはもどれないこと、この世の未練を断ちきつて浄土に進むしかないことを、悟らせるわけです。
それが「引導を渡す」という意味であり、葬儀を行う意義なのです。ただ引導を渡したからといって、すべての人がただちに納得するわけではありません。
「おれは死んでなんかいないんだ」と拒否されることもあります。
さらには、「本人」のもともとの性格もあります。
生きている人間がさまざまなように、故人の性格もさまざまです。
生前、ものわかりの悪かった人が、死んだからとい。てものわかりがよくなることはありません。生前、頑固だった人が死んで素直になるといったことはありません。疑り深い人は、死後も疑り深い.あきらめの悪い人は、死んでもあきらめが悪い・。生前の性格は死後もそのままなのですから、自分の死をなかなか認めようとしない人もいるわけです。また、なかには未練や執着があまりに強かったり、疑り深い性格などから、自分の死をまったく納得しないでいる人もいます。そうなりますと、この世で亡霊となって長い間さまようこともありうるわけです。
だから、繰り返し繰り返し「あなたは死んだのだ」ということを伝えるために、葬儀の後にも法要を重ねていく必要があるのです。
「本入」が死を自覚するまでの期間はどれくらいか
自分の死に気がつかない人が少なからずいると申しました。また白分の死に気づくまでには、多少の時間がかかるものなのです。死んだからといって、その直後に自らの死を白覚するというのではなく、次第に時とともに自覚していくのだと思われます。
そこで、通夜、葬儀、初七日、四十九日と回を重ねていくうちに、何度も何度も「あなたは死んだのですよ」と伝えていくことになります。こうして回を重ねていくことよって、「本人」も次第に自分の死を自覚していくことになるのです。自分の死を悟ることによって、「本入」がこの世の執着を棄てて成仏の方向に向かうのです。
私が「本人」を感じるのも、亡くなってすぐのときがやはり一番強く、法要の数を重ねて時を経るにしたがって、徐々に薄くなっていきます。それは「本人」がこの世の執着や未練を葉てていくことと比例しているようです。
さて、「本人」が自らの死を自覚するまでの期間は、いったいどれくらいなのでしようか。
仏教では、死の瞬間から次の生を受ける間を、中陰(中有)といって、その期間を四十九日としており、七日ごとに法要を営んできたのです。私自身の葬儀と法要の体験からしても、いわゆる未練がおおかたなくなったと思わる区切りは、まあ平均的には四十九日ということができます。ただもちろん、これには個人差があります。早い方ですと二、三週間でそこまでいたる人もいますし、遅い方ですと二、三年もかかる場合もあります。
しかし、ときには大変な長い期間にわたって自らの死に気がつかない場合もあるのです。たとえば、十分に葬儀や供養をせずに放っておかれたときがそうです。突然の交通事故で亡くなり「本人」はそのままの事故現場にいて、自分が死んだという自覚がない場合もそうです。そして、この世に対する未練があまりに強烈だった場合もそうです。
極端な場合には、何十年、何百年、いや何千年も時空を超えて残る場合もあるのです。これが、いわゆる「呪縛霊」とか「地縛霊」 などと言われるもののことです。平家の怨霊話とか、いろいろと各地で伝えられているのがそれです。
わが亡きあとに洪水はきたれ!
先ほど、就寝前の歯磨きをしていたら、ひょっこりと輪廻転生が頭に浮かびました。輪廻があるのかどうなのかは?ではありますが、輪廻転生を信じる方が世界にはやさしいような気がします。ならば、信じてもよいのかななどと考えておりました。
輪廻転生がないと「わが亡きあとに洪水はきたれ」という言葉が重くなってくるなあということが、次に脳裏に去来しました。
このフレーズは、わが亡きあとに洪水はきたれ!―ルポルタージュ 巨大企業と労働者 (ちくま文庫)で知ったものです。フレーズの由来については、日本共産党の宮本たけしさんのブログに詳しく掲載されていて勉強になりました。『あとは野となれ山となれ』という意味だそうですが、その説明部分のみ参考までに下記に掲載させていただきます。
「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!」とポンパドゥール侯爵夫人
この間、志位さんがサンデープロジェクトで紹介してから口の端にのぼるようになった「資本論」でマルクスが引用した言葉「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!」…この言葉が出てくるのは「資本論」第一部(1巻)第三篇第八章の「労働日」。第五節の「標準労働日獲得のための闘争。14世紀中葉から17世紀末までの労働日延長のための強制法」の中ほどに出てきます。(社会科学研究所監修、資本論翻訳委員会訳、新日本新書版なら、第2分冊、P.464)
次のように出てきます。「どんな株式思惑においても、いつかは雷が落ちるに違いないということは誰でも知っているが、自分自身が黄金の雨を受け集め安全な場所に運んだ後で、隣人の頭に雷が命中することをだれもが望むのである。“大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!”これがすべての資本家およびすべての資本家国民のスローガンである。それゆえ、資本は、社会によって強制されるのでなければ、労働者の健康と寿命にたいし、なんらの顧慮も払わない」
ただしマルクスはすぐその後で「しかし、このこともまた、個々の資本家の善意または悪意に依存するものではない。自由競争は、資本主義的生産の内在的な諸法則を、個々の資本家にたいして外的な強制法則として通させるのである」と、付け加えるのを忘れませんでした。つまり「大洪水よ、わが亡きあとに来たれ!」というのは、資本家の性格が性悪だからそうなるといったものではなく、逆に、資本主義的生産の内的な法則性が競争を通じて資本家にそういった行動を取らせるのだというわけです。
さて、そこでこの「大洪水よ…」ですが、「資本論」の注釈には「宮廷の奢侈が財政破滅を招くと忠告されたときに、フランスのルイ15世の愛人ポンパドゥール夫人がノアの洪水伝説にちなんで言った言葉の言い換え。デュ・オセ夫人『回想録』、序文、19ページ。『あとは野となれ山となれ』の意」とあります。
・・・以下略・・・
これが、死んでも生まれ変わるということになると「野となれ山となった」ところでまた生きていかなければならないわけですから、そうもいかないなあなどと考えることになるかもしれませんね。輪廻説は地球にやさしい考えなのかもしれません。
私の学生時代、マルクスは反体制の必需品で、反資本主義の先鋒でもありました。しかし、今になって思うに資本主義の対極にあるのではなく、資本主義の裏側にあったのではないかと思います。表に対する裏。表裏一体という言葉があるように、マルクスは資本主義を超えるものではなく、まさに資本主義そのものを語っていたのだなあとおもうのです。そして、その番い(つがい)の部分こそ、この「輪廻転生」にあるのではないかと思っているのです。
フランスのルイ15世の愛人ポンパドゥール夫人のこのせりふで、記憶がよみがえるのが頭脳警察の「さよなら世界夫人」です。ユーチューブでは、http://youtu.be/Ao6Yyz6nEYoで聴くことができます。これは、ただ単に私が関連付けて記憶しているだけで、実際にはなんの関連もありません。学生時代に周りでやたらとヒットしていたような気がします。曲も詩もよく思われ、たまに無性に聴きたくなる時があります。私の中では、プロコルハルムの「青い影」と同じ位置にある楽曲ですね。ユーチューブでは、http://www.youtube.com/watch?v=buSzOh84QX4で聴くことができます。
どちらも、詩がよくわかりません。
エンディング・ノートは、団塊の世代「最後」の大量生産化か?
エンディング・ノートは考えれば考えるほどわからなくなる映画だ。死にたいと思っている人も世の中には沢山いるから、そういう人にとってはためになると思うが、生きたいと思っている人はそれ以上沢山いると思うので、そういう方々には良くない映画だと思う。
世の中には「願望成就法」なるものが多く存在しているが、そのなかでも定番なのが、ノートに自分の夢をできるだけ具体的に書いてみるという方法だろう。例えばお金持ちになりたいという方は、具体的に金額を書く。10億円とか、100万円とか。車が欲しいという方は車の名前を書いてみる。ベンツ500SL(こんな車あるかなぁ?、興味がないので確証ありません)とか。
エンディング・ノートは、この「願望成就法」をなぞったもの。ということは、つまり、お父さんは、死にたかったといえるのではないでしょうか。この映画でわかることは、具体的にノートに書き連ねた言葉は力をもち、家族や医者、および関連スタッフに共通の認識と力を与え、死の具現化のためまっすぐにゴールへと突進してしまったということです。ドキュメンタリーながら、この映画のエンディングシーンは、作り込まれたものとなり、つまらないものになってしまいました。
誕生や死は、たとえば、ゲーテが、最後に「光をもっと光を」といったり、道長が、「極楽浄土」を願ってひもを手にとったり、人生の中でも、作為的な嘘のようなものが入る隙のない、当事者の真実がほとばしる数少ないシーンの一つであると思うのですが、お父さんは最後の最後を当たり前といえば当たり前の普通名詞の「死に際」にしてしまいました。それがいいんだ、といわれれば、何ともいいようがありませんが、それでも、結局、このお父さんは何者だったの?という疑問が私の中では残り続けております。
大会社の取締役とのことだが、業績は残したのかな、一つ二つは紹介してもらいたかった。就職以前、進学などには自分の意志は介在したのだろうか、先生とか進路指導のまま考えることなく進学、就職したのだろうか。奥さんとは恋愛なのだろうか、挫折体験はなかったのだろうか。夫婦関係、親子関係はどうだったのだろうか。かなえた夢は、最後の死以外にあったのだろうか。疑問はキリがないが、・・・なにも見えない。
ソニーとの取引に失敗したとのことだが、それはそのままだったのだろうか。反省はあったのだろうか、あったとしたらそれはどのように生かされたのだろうか。仏教の葬儀はお金がかかるということでキリスト教にしたのだが、いくら節約になったのだろうか。仏教とキリスト教以外の選択は何があったのだろうか、なかったのだろうか。節約ということなら、究極として墓などいらないということにはならなかったのだろうか。川とか海に灰を投げるというのはどうだろうか。
キューブラー・ロスは「最終的に自分が死に行くことを受け入れる段階」として死の受容のプロセス(否認→怒り→取引→抑うつ→受容)を表しているが、そのようなものはこの映画では見られなかった。このプロセスは、否認とか怒りの間に、医師や医療への疑問とか怒りを経ることになり、たとえば、病院や医者を変えてみたり、丸山ワクチン(今もあるのかな?)ゃ他の療法を試したりということになるのだが、お父さんはそのような事はなかったのだろうか?治るとか治療するという、つまり生きる意志がそもそもあったのだろうか。なにも見えないのだ。最後までなにも見えないのだ。映画はひたすら、凡庸な死にむかっていくだけだ。
普通は、そうだなあ、家族の中にも「鬼っ子」みたいな、出来損ないで頭や素行が悪いのがいて、それが、映画を撮っているのに怒ってスタッフを蹴り散らかしたり、医者に悪態を付いたり、無理矢理退院させたり、理屈じゃできないことを平気でやらかして、その場や空気に冷や水を浴びせたりして、結果的にお父さんを救ったり、そこまで行かなくても、遺産相続なんかでもめて、葬儀をめちゃくちゃにしたりして、生気あるお父さんの一生を創り上げたりしないかなと思うんだけどなぁ、どうなんだろう。
懸念するのは、ベビーブームでうまれて、ベルトコンベアに載りっぱなしで生きてきて、気が付いたら死が近づいてきた。とはいえ、ベルトコンベア以外の選択は経験がないため、そのままベルトコンベアにしがみついてしまったら死んじゃったということだった・・・、そういうことだったのではなかろうか?そんなことがあるのだろうか?・・・、十分にありそうだな。家族のあり方を含めて、考えさせられる映画ではありました・・・。
最後に、E・キューブラー・ロスの貴重な講演集「死後の真実」巻末にある、阿部秀雄の解説き部分(キューブラー・ロスの略歴みたいになっている)を以下に紹介したい。キューブラー・ロスの「死」に対する真摯さに鑑みてこの映画を精査すれば、わたしがこの映画にもつ疑問が少しでも理解していただけるのではないかと思う。
死のセミナーの時期
エリザベス・キュープラー・ロスは一九二六年、スイス、チューリヒで生れた。義務教育を終えると、父親の反対を押し切って医師への道をめざした。住み込みの家政婦などをして働きながら大学入学の資格を取り、一九五七年チユーリッヒ医科大学を卒業する。結婚してアメリカに渡り、一九六五年にシカゴ大学に研究員として入局してから、りん死患者のベッドサイドを訪れて、死にゆく人の話し相手になり、悲しみの克服と死の受容を助けるという、これまで誰も手を付けようとしなかった仕事を始めた。
数多くの患者と体験を共にするうちにロスは、重症のがんだという衝撃的な宣告を受けた患者が経ていく心の動きに共通するものがあることに気づく。まずはその事実をかたくなに否認することから始まって、怒りを激発させ、取り引きを試み、あきらめて悲嘆に沈む時期を経て、安らかに死を受容してこの世に別れを告げるまでの五段階である。後になってこれは、たんに、りん死の体験にかぎったことではなく、その人にとってかけがえのない大切なものを喪失するときつねに体験する現象だということが明らかになった。
シカゴ大学に入局してまもなく「死のセミナー」を開始し、一九六九年には『死ぬ瞬間』を出版した。この最初の著書がベストセラーになり、また国際的なライフ誌で大きく取り上げられるなどしてその業績が広く世に知られるにつれて、ロスはアメリカ国内はおろか、世界各地を超多忙のスケジュールで飛び回るようになる。なお、ここで紹介しているロスの半生については、デレク.ギル著『「死ぬ瞬間」の誕生』〔貴島操子訳、読売新聞社)を参照した。
医者が生かすことでなく死ぬことに目を向けるなどというのは、当時としては異端視さえされかねない画期的な仕事だったが、今日では終末期医療やホスピスの先駆者として高く評価されている。この時期のロスの仕事を特徴づけるキーワードは、来るべき<死>ないしは<喪失>の〈受容〉をどう援助するかであった。
癒しのワークショップの時期
少数の人たちを相手にもっと深い交流ができるのではないかと思うようになったロスは大学を辞め、病床で個々の患者と輝くような最期のひとときを共にするほか、集団による癒しのワークショップに力を入れるようになる。最初のワークショップが試みられたのは一九七〇年。これが成功に終わったので各地で開かれるようになったが、やがて一九七七年になるとシャンティ・ニラヤと呼ばれる本拠地が建設される。
時とともに、ロスが主宰するワークショップは、りん死患者のための死への癒しにとどまらず、広くさまざまな苦悩をかかえた人々を含めた、生と死の癒しの場へと発展していく。五日間のワークショップに参加した人たちは、いつしか心のよろいをはずして感情を解き放ち、心ゆくばかり怒りをぶつけ号泣したあとで互いに抱き合い、許し合い、じぶんと他人を愛する力を取り戻して、まるで別人に生まれ変わったかのように、見失っていた自じぶんを取り戻す。
この時期の特徴は、来るべき死に気持ちを向ける前にまずベクトルを逆にして、生まれてからこの方、根深いところに閉じこめてきた苦痛の感情を、無条件の愛に包まれた安心感に支えられて解き放つのを助ける仕事が本格化してきたことである。キーワードは過ぎ去った<生>の<癒し>であり、そのことで残されたこれからの生がますます輝きを増すことになる。
それとともに、りん死患者の体験やじぶんじ身の神秘的な体験に促されるようにして、合理的な医学教育を受けてきたはずのロスはしだいに、死後のいのちへの確信を深めていく。過去の癒しとともに未来からの希望が、いわば両面からりん死患者を支えるようになる。でも、それについては、この時期にはまだまだあまり声高に言われることは少なく、副次的な位置を堅持していた。
ロスにはこれまでに多くの著書があり、最初の著書『死ぬ瞬間』〔原著一九六九年)をはじめとして、『死ぬ瞬間の対話』(一九七四年)、『続・死ぬ瞬間』(一九七五年)、『死ぬ瞬間の子供たち』(一九八一年)、『新・死ぬ瞬間』(一九八三年)、『エイズ死ぬ瞬間』(一九八七年)の六冊が、デレク・ギルによる伝記『「死ぬ瞬間」の誕生』(一九八○年)とあわせて「死ぬ瞬間」シリーズの形で読売新聞社から刊行されている。また、E・キューブラー・ロス文/M・ワルショウ写真『生命ある限り-生と死のドキュメント』(一九七八年)と『生命尽くして-生と死のワークショップ』(一九八二年)が産業図書から刊行された。
こうした一連の著書をいま読み返してみると、死後のいのちに関するロスの確信が、実はかなり早い時期から少しずつ、控えめな形で表明されてきていることに気づく。すでに二冊目の、一九七四年の著書『死ぬ瞬間の対話』のなかで、質間に答える形で、「死後のいのちを一点の疑いもなく信じている」「肉体は死ぬが精神ないし霊魂は不死だと信じている」と、言栞少なにだがきっぱり言い切っている。翌七五年に出された『続・死ぬ瞬間』では、「ケムシがチョウになるように」という比喩が現れる。しかし何かと考えるところがあったにちがいない。こうしたことを正面から著書に書くことにはかなり慎重だったようである。
『ダギーへの手紙』と『天使のおともだち』
その例外の一つが文中にも出てくる『ダギーへの手紙』〔アグネス・チャン訳、はらだたけひで絵、佼成出版社)である。これは、一九七八年に九歳の脳腫瘍にかかった男の子ダグ・トゥルノからもらった手紙で投げかけられた、「いのちとは何なの?死ぬってどういうこと?子供が死ななくてはならないの
はなぜ?」という切実な質間に心を打たれたロスが、この本で曹かれているのと同じような内容をはっきりと、子供にも分かるようにやさしくかみくだいて、フェルトペンを使った色彩豊かなイラストを添えて出した返事である。ダギーの宝物になった手紙は、手から手へと渡されて多くの親子に読まれていたが、とうとう手書きの字や絵をそのままに出版された。
この十ページほどの、まるで絵本のような小冊子のなかで、ロスは何よりも神様の愛を強調している。ちょうど太陽のように、神様の愛はいつでも、たとえ雲にさえぎられて私たちの目に見えないときでさえ、私たち一人ひとりをあたたかく照らしてくれていること、その愛は無条件の愛であること、子供は神様に送られて自分の親を選んで生まれてきたこと、親の成長や学習を助けることができること。
生きるとはちょうど学校のようなもので、私たちは生きているあいだに、愛すること愛されることを含めていろいろなことを学ばなくてはならないこと、
神様がら出された試験に合格すると、そこを卒業して私たちがやってきた古巣に帰ることができること、そこはもう痛みなどなく、親しい人たちと再会し、楽しく歌ったり踊ったりできること。
「死ぬことはマユから抜け出て美しいチョウになるようなものだ」という比喩がここで絵入りで使われている。「春に捲かれ、夏に咲き、秋に実り、冬に枯れる」とか、「水平線のかなたに行ってしまった船は目に見えなくなるだけで、消えることなどないのだ」とか、「夜になってもまた朝がくる」とか、いろいろなたとえを使って、死後も続くいのちについて伝えようとしている。
もう一つの例外が、一九八二年に書かれた『天使のおともだち』(伊藤ちぐさ訳、金子千晶絵、日本教文社)というすてきなファンタジーである。男の子ピーターが重い病気にかかって死に、ピーターを愛していたおとなたちも、大なかよしだった女の子のスージーも悲しみの涙を流すが、スージーの悲しみはおとなたちとはちょっと違っていた。それというのも、ふたりはいつも天使と一緒に遊んでいろいろなことを話していたし、ピーターが亡くなる少し前に天使に導かれて肉体を離れ、愛としあわせに満ちた美しいあちらの世界に旅したことがあるからだった。
本来の仕事と取り組む時期
ところが、ワークショップの仕事が軌道に乗ってきた頃ロスは、本文に書かれているように、死にゆく患者を椙手の役目はもう終わった、という啓示を受ける。すでにロスの代わりとなる人はたくさんいるし、ロスがこの世にいる当の理由は、死は存在しないという〈死後の真実〉を人々に伝えることであって、これまで取り組んできたことは、この仕事をやりぬくための苦難や酷使や抵抗に耐えることができるかの試験台だった、というのである。
こんなふうに死にかかわるロスの仕事の歩みを三つの時期に分けてみたが、もちろんこれは便宜的なもので、新しい時期の仕事を特徴づける要素は古い期に芽生えているし、新しい時期を迎えたからといって古い時期の仕事の意味が薄れるというものでもない。
それにしても、あらゆる時期を一貫して特徴づけるキーワードは何かと間われれば、それは無条件の〈愛〉のエネルギーだと答えたい。
現代のシャーマン
重症の患者から臨死体験についていろいろ見聞きするのと前後して、ロス自身も霊的な存在との触れ合いや超越的な体験をすることが、死ぬ瞬間を共にする仕事を始めるずっと前からいろいろあったらしい。
愛と霊感のカを借りて、この世の生と死後の世界とを仲立ちする人ー。これはまさにシャーマンだが、ロス自身も、自分はシャーマンだと称してはばからない。これには、行ったこともないインディアン部落の夢見や、実際に部落を訪れたときの懐かしい既視感や、催眠退行による体験がからんでいて、ロスは自分がかつて前世でインディアンだったと信じているようなのである。
当時朝日新聞社の編集委員だった飯塚真之さんが取材した「こころ」の頁(朝日新聞、一九九〇年十二月三日朝刊)によると、ロスは、親交のある精神科医の卜部文麿(うらべふみまろ)さんに向かって、「あなたもシャーマン、私もシャーマン、インディアンのシャーマンは癒しを意味するが、私たちも現代の医師として立派なシャーマンです」と語り、「私は2003年まで生きます〔七十七歳になる)。あなたもそれまで生きてください。でもその年に死ぬことが決まっています。なぜって、昔からそう思っていた」とも語ったという。
死後の真実がはたしてロスの言っているとおりかどうかについては異論もあるかもしれない。しかし、ロスの偉大なところは、たんにりん死体験について世界で最初に関心を持ち本格的な研究をしたのがロスだった、というだけではない。興味とか研究とかの前に、何よりも死に臨む人たちとの深い愛と学びに動機づけられているところが私たちを感動させるのではないだろうか。
人類全体が長いこと物質本位に走り続けたあげく大きな危機にさしかかっいる今日、この本は、私たちに見えない世界を見るように促し、新たな目覚を誘う重要な意味を持っているように思う。
【付記】本書が刊行されてから、キューブラー・ロスの著書が二冊邦訳された。一冊は『「死ぬ瞬間」とりん死体験』(鈴木晶訳.読売新聞社)で、本書と同じようなテーマについて取り上げた七つの講演を集めたもの。多少重複する内容もあるが、これはこれで一読に値する。もう一冊は『人生は廻る輪のように』(上野圭一訳、角川書店)で.これはロス博士自身の手によって書かれた自伝である。デレク・ギルによる伝記『「死ぬ瞬間」の誕生』の記述が一九六九年末、つまり「死のセミナーの時期」で終わっているのに対して、それ以後の「癒しのワークショップの時期」、さらには、死後の真実を人々に伝えるという「本来の仕事と取り組む時期」についても多くのページが割かれている。仕事から引退した七十一歳のロスはこれが事実上の絶筆になるだろうと述べている。
【付記2】二〇〇四年八月二十四日、ロスは自分が予感していた時期より一年だけ遅れて、マユから抜け出して美しいチョウになった。